�����T�C�g�͈�Ï]���҂��ďC�E�^�c���Ă��܂���
�X�����̍R������Ái���w�Ö@�j

�@�X�����͑���������������߁A�����̏ꍇ�Ŏ�p���s�����A�R������Â��I������܂��B�R����܂Ŋ�����ڎw�����Ƃ͍���ł����A����������������A�i�s��x�点����A�ɂ݂��y�����Ăp�n�k�����コ������ʂ����҂ł��܂��B
�ڎ�
- �R������Ái���w�Ö@�j�Ƃ�
- ���Âɂ�����R����܂̖ړI
- �X�����őI�������R����܂̎��
- ���Â͂ǂ̂悤�ɐi�߂�H
- ���Âɔ�������p�͑��v�H
- �R����܂̗L�����ƈ��S��
- ���w�Ö@�Ƃ͂ǂ�Ȏ��ÁH
�R������Ái���w�Ö@�j�Ƃ�
 �@�R������ÂƂ́A�R����܂�_�H������œ��^���A���t�������đS�g�ɉ^�ꂽ�R����܂����זE���U�����j����̂ŁA���w�Ö@�Ƃ��Ă�܂��B��p�����ː������͌���ꂽ���ʂɑ��Ă̎��Âł���̂ɑ��A�R������Â̑Ώۂ͑S�g�ɋy�т܂��B
�@�R������ÂƂ́A�R����܂�_�H������œ��^���A���t�������đS�g�ɉ^�ꂽ�R����܂����זE���U�����j����̂ŁA���w�Ö@�Ƃ��Ă�܂��B��p�����ː������͌���ꂽ���ʂɑ��Ă̎��Âł���̂ɑ��A�R������Â̑Ώۂ͑S�g�ɋy�т܂��B
�@�����̍R����܂̃��J�j�Y���́A�זE������ۂ̂c�m�`�̍�����W������̂ł��B����זE�͒ʏ�̍זE�����p�ɂɍזE������J��Ԃ����߁A����זE�̕����W���čזE���B��}���铭��������܂��B
�@�������Ȃ���A����זE�������^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��Ȃ����߁A���Ȃ��炸�ʏ�̍זE�ɂ��e����^���Ă��܂��A���̌��ʕ���p���������܂��B���݂̂Ƃ���A�R����܂����Ŏ��Â��ł�����͂����ꕔ�ɂ������A�X�����͍R����܂������ɂ������̂P�ł��B
�@�������A���ʂ�����ɂ����Ƃ����Ă���������L�����͉\�ŁA���Ö@���N�X�m������Ă��܂��B
�X�������Âɂ�����R����܂̖ړI
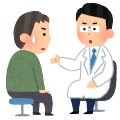
�@�X�����͐i�s��������ɔ�������ɂ������ł��B���̂��߁A�������ꂽ���ɂ͂��łɊ������Ȃ�i�s���Ă���A��p���s���Ȃ��P�[�X�����Ȃ�����܂���B
�@�匌�ǂւ̐Z���A���x�ȃ����p�ߓ]�ځA�x��̑��ւ̉��u�]�ڂ��F�߂���X�e�[�W�Wa�A�Wb���X�����ł���p�ɂ��؏�������A���̏ꍇ�͍R������Â����ː����������S�ɍs���܂��B
�@��p���ł����ꍇ�ł��A�Ĕ����Ă��܂����ꍇ�ɂ͍R������Â��s���܂��B�Ĕ����Ă��܂������͍Ď�p������ȃP�[�X���قƂ�ǂł��B�܂��A���̓E�o��p�Ŏ��c���Ă��܂��ڂɌ����Ȃ������Ȋ����傫���Ȃ��čĔ�����̂�\�h������A�]�ڂ��Ȃ����Ǐ��I�ɐZ���������ꍇ�ɂ́A������ڎw���Ď��Â��s�����Ƃ�����܂��B

�@�X�����͍R����܂����Ŋ�����ڎw�����Ƃ͍���ł����A�����������Ȃ�����A�傫���Ȃ�X�s�[�h��}�����肷����ʂ͑�������Ă��܂��B
�@���̌��ʂɂ���Ēɂ݂₳�܂��܂ȏǏy�����A�p�n�k�̉��P�ɂ��Ȃ����Ă��܂��B�܂��A�܂�Ɋ����������Ȃ��Ď�p�ɂ��؏����\�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�X�����őI�������R����܂̎��
�@�X�����ɑ���R������Â͔N�X�i���𐋂��Ă���A�ȑO�ɔ�ׂ�R����܂̑I�������L�������ق��A���^���@��g�ݍ��킹�Ȃǎ��Ö@�͊i�i�ɐi�����Ă��܂��B
�@1990�N���܂ł̓t���I���E���V�������R����܂̑I����������܂���ł������A�����Ď��Ì��ʂ��悢�ƌ�������̂ł͂���܂���ł����B2000�N�߂��ɂȂ��ăQ���V�^�r���i���i���F�W�F���U�[���Ȃǁj���J������A�t���I���E���V���ɔ�ׂĊi�i�Ɏ��Ì��ʂ��������Ƃ��m�F����Ă���́A�Q���V�^�r�����X�����̕W���I���ƂȂ�܂����B
 �@���̌�A���{�ɂ����ăG�X�����ƌĂ��R����܂��J������A�Q���V�^�r���ɗ��Ȃ����A��������鎡�Ì��ʂ��m�F����Ă��܂��B�܂��A��荂�����Ì��ʂ�_���čR����܂�g�ݍ��킹�Ďg�p���鑽�ܕ��p�̎��Ö@���J������Ă��܂��B
�@���̌�A���{�ɂ����ăG�X�����ƌĂ��R����܂��J������A�Q���V�^�r���ɗ��Ȃ����A��������鎡�Ì��ʂ��m�F����Ă��܂��B�܂��A��荂�����Ì��ʂ�_���čR����܂�g�ݍ��킹�Ďg�p���鑽�ܕ��p�̎��Ö@���J������Ă��܂��B
�@�Q���V�^�r���ɕ��q�W�I���Ö�̃G�����`�j�u�i���i���F�^���Z�o�j��g�ݍ��킹�鎡�Ö@�̂ق��A2013�N�ɂ�FOLFIRINOX�Ö@���A2014�N�ɂ̓Q���V�^�r��+�i�u�p�N���^�L�Z�������{�ŏ��F����Ă��܂��B
�@���̂��߁A���݂��X�����ɑ���R������ẤA�@�Q���V�^�r���P�ƁA�A�G�X�����P�ƁA�B�Q���V�^�r��+�G�����`�j�u�A�CFOLFIRINOX�Ö@�A�D�Q���V�^�r��+�i�u�p�N���^�L�Z���̂T����I�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�X�����ɂ�����R������Â̐i�ߕ�
�@ �R������Â̕��j�f����
�@�R������Â͐g�̓I�ɂ��̗͓I�ɂ��e����^���邽�߁A���҂̑S�g��Ԃ��ǍD���ǂ����A�S����̑��Ȃǂ̎�v�ȑ���̋@�\���x�������ȏ�ɕۂ���Ă��邩��]�����A�̗͖ʂ��܂߂čR������Â��s���邩�ǂ����A���^����œK�Ȗ�܂̎�ނ͉����Ȃǂf���܂��B
�@�ʏ�A�R������Â͎��͂ł̕��s���\�ȑS�g��Ԃ̊��҂ɑ��čs���A�����̔����ȏ���x�b�h��֎q�ʼn߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǂ̏ꍇ�ɂ́A�R������Â����ɘa���Â����߂��܂��B
�@���҂͈�t���瓊�^�X�P�W���[���╛��p�̃��X�N�ɂ��ď\���Ȑ������A��t�Ɗ��҂Ŏ��Ö@�����߂܂��B
�A �R����܂̓��^�J�n
�@���Õ��j�����܂�R����܂̓��^���n�܂�܂��B�R����܂͓����Ɠ_�H�̂��̂����邽�߁A���^�����܂ɂ���ĊO�������@�ōs�����ƂɂȂ�܂��B�R����܂͕���p�����߁A���^�����͓��@�ōs���A��肪�Ȃ���ΊO���ɐ�ւ���ꍇ������܂��B
�@�ŋ߂ł͏���O���Ŏn�߂�a�@�������Ă���A���@�ł̓��^������p�̒��x�����e�͈͓��ł���A���@���Ԃ͐����ԂƂȂ�܂��B
�B ���Ì��ʂ̊m�F
�@����p�ɂ�铊�^�̓r�����f���Ȃ��ꍇ�A���N�[���̓��^���s�����̂��ɁA�ǂꂭ�炢���Ì��ʂ����������̕]�����s���܂��B�a�����̏�ԁA�R����܂Ƃ̑����ɂ���Ď��Ì��ʂɍ�������邽�߁A���^��Ɏ��Ì��ʂ�]�����邱�Ƃ͂ƂĂ���Ȃ��Ƃł��B
�@�]���͒ʏ�Q�������ƂɎ��{���A��ᇃ}�[�J�[�̑����A�b�s�����ɂ���ᇂ̑傫���̔�r���s���܂��B��{�I�ɂ͎�ᇂ����ÑO�������債����A�V���Ȏ�ᇂ��������Ă��Ȃ���Ύ��Ì��ʂ��������Ɣ��肵�܂��B
�C ���^�̌p���܂��͕ύX
�@�R����܂ɂ�鎡�Ì��ʂ��F�߂��A����p�����e�͈͓��ł���A�R����܂̓��^�͌p�����܂��B���Ì��ʂ͔F�߂��邪�A����p�����e�͈͂���ꍇ�́A��������x����A���^�ʂ����炵�Čp�����邱�Ƃ�����܂��B
�@���Ì��ʂ��m�F�ł��Ȃ��ꍇ��A�ŏ��͌��ʂ����������̂́A�ϐ��ɂ���Ď��Ì��ʂ��Ȃ��Ȃ����ꍇ�́A���^�����܂̕ύX���������邱�ƂɂȂ�܂��B
���Âɔ�������p�͑��v�H
�@�R����܂ƕ����ƁA��͂�S�z�Ȃ͕̂���p�ł��B�R����܂̃��J�j�Y��������킩��悤�ɁA�R����܂͂���זE�������^�[�Q�b�g�Ƃ��Ă��Ȃ����߁A�ʏ�̍זE�ɂ��e����^���Ă��܂��܂��B
 �@����p�Ƃ��đ�\�I�Ȃ��̂ɁA�f���C�A�q�f�A�����A�H�~�s�U�A�������ȂǏ�����Ɋ֘A��������p�̂ق��A�畆�̐F�f�����A���т�Ȃǂ̐_�o��Q�A�E�тȂǂ�����܂��B
�@����p�Ƃ��đ�\�I�Ȃ��̂ɁA�f���C�A�q�f�A�����A�H�~�s�U�A�������ȂǏ�����Ɋ֘A��������p�̂ق��A�畆�̐F�f�����A���т�Ȃǂ̐_�o��Q�A�E�тȂǂ�����܂��B
�@�܂��A�����ł͑����זE����Ԍ����┒�����A�����Ȃǂ������Ă��܂����A���̑����זE���j��邱�ƂŌ��t�זE���������A�Ɖu�͒ቺ��n���A�o�����N������������܂��B������n�̕���p�͎��o�Ǐ͂����肵�Ă��锽�ʁA�����}���ɂ�镛��p�͎��o�Ǐo�ɂ�������p�ƌ����܂��B
�@�̑���t���ɏ�Q������ꍇ�A�R����܂̑�ӂ�r���������Ȃ�A�����Z�x�������Ȃ邽�߂ɕ���p�Ǐ�������鎖������܂��B���̂��߁A���҂̐t�@�\��̋@�\���ቺ���Ă���ꍇ�́A�ʏ�����R����܂̎g�p�ʂ����Ȃ�����Ȃǔz�����K�v�ƂȂ�܂��B
 �@����p�͓��^�ʂ����Ȃ�������A���~�����肷��Ƒ����̏ꍇ�ʼn��܂����A�Ԏ����x���Ƃ����ċz�펾���ǂ����ꍇ�͓��^�𒆎~���Ă������A�t�ɏd�lj�����ꍇ������܂��B�Ԏ����x���͔x�̍זE����Q���Ĕ��ǂ�����̂ŁA������P�A���M�Ȃǂ̏Ǐ���܂��B
�@����p�͓��^�ʂ����Ȃ�������A���~�����肷��Ƒ����̏ꍇ�ʼn��܂����A�Ԏ����x���Ƃ����ċz�펾���ǂ����ꍇ�͓��^�𒆎~���Ă������A�t�ɏd�lj�����ꍇ������܂��B�Ԏ����x���͔x�̍זE����Q���Ĕ��ǂ�����̂ŁA������P�A���M�Ȃǂ̏Ǐ���܂��B
�R����܂̗L�����ƈ��S��
 �@�R����܂͊��זE�ɑ��鍂�����Ì��ʂ����߂��锽�ʁA����p���ł��邾�����Ȃ�����K�v������܂��B���̂悤�Ɏ��Ì��ʂƕ���p���w�����킹�Ȃ̂��R����܂ł����A�ŋ߂ł͐V��⎡�Ö@�̊J���ɂ���ĕ���p�͊i�i�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�@�R����܂͊��זE�ɑ��鍂�����Ì��ʂ����߂��锽�ʁA����p���ł��邾�����Ȃ�����K�v������܂��B���̂悤�Ɏ��Ì��ʂƕ���p���w�����킹�Ȃ̂��R����܂ł����A�ŋ߂ł͐V��⎡�Ö@�̊J���ɂ���ĕ���p�͊i�i�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��܂��B
�@�܂��A����p��}�����̊J�����i��ł���ق��A�g�p�ʂ�g�ݍ��킹�Ȃǂ��������A���Ì��ʂƈ��S�����ő剻����悤�ȓ��^�ʂ�g�p���@��Տ������Ō����Ă��܂��B�������Ȃ���A����p�����邱�Ƃɂ͕ς�肠��܂���B
�@��t����R������Â�i�߂�ꂽ�ꍇ�́A�g�p����R����܂̌��ʂ�g�p���鎖�ɂ�闘�_�A����p�ɂ��ď\���Ȑ�������悤�ɂ��܂��傤�B�����āA�\���Ɏ������[��������Ŏ��Â��J�n���鎖����ł��B
���w�Ö@�Ƃ͂ǂ�Ȏ��ÁH
�@�X�����ɑ��ď��߂čs���R������Â��ꎟ���w�Ö@�ƌ����܂��B�ꎟ���w�Ö@���J�n���Ă���A���^���Ă���R����܂����ɑ��Č��ʂ��Ȃ��������Ă��܂�����A����p�������Ď��Â𒆒f������Ȃ����Ƃ�����܂��B
�@�R����܂𒆎~�����̂��A���҂̏�Ԃ��m�F���čĊJ����R������Â���w�Ö@�ƌ����܂��B���w�Ö@�͒ʏ�A�ꎟ���w�Ö@�Ŏg�p�����R����܂Ƃ͈قȂ��ނ�I�����܂��B
�@���w�Ö@�łǂ̂悤�ɍR����܂𓊗^����ׂ����A���Ö@�͂܂��m������Ă��炸�l�X�ȗՏ��������s���Ă��܂����A���w�Ö@���s���������s��Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂĐ������Ԃ����т鎖�͂킩���Ă��܂��B
�@���ݍs���Ă���ꎟ���w�Ö@��傫��������ƁA�Q���V�^�r�����܂ގ��Ö@�ƁA�t�b���s���~�W���n��܂��܂ގ��Ö@�iFOLFIRINOX�Ö@�A�G�X�����Ö@�j�̂Q������܂��B
�@�ʏ�A���w�Ö@�͈ꎟ���w�Ö@�Ƃ͈قȂ�R����܂�I�����܂��̂ŁA�ꎟ���w�Ö@�ɃQ���V�^�r����I�������̂ł���A���w�Ö@�̓t�b���s���~�W���n��܂�I������A�ꎟ���w�Ö@�Ƀt�b���s���~�W���n��܂�I�������ꍇ�́A���w�Ö@�ɃQ���V�^�r����I������̂���ʓI�ł��B




















